【更新日:2025年07月11日】
この記事はこんな人に向けています:
・中国人観光客の「声の大きさ」にストレスを感じている方(声がとにかく大きい)
・中国人との共同生活で音問題に困っている方(スマホでTikTokを大音量で再生している・テレビの音をリモコンで下げても、すぐまた上げられる)
・なぜ中国人はあんなに音に鈍感なのか、文化背景を知りたい方
この記事では、「中国人は話す声が大きいだけではなく、耳で聞く音も大きい」というテーマを文化背景から解説します。
中国では「大きな音=悪いこと」とは限らず、にぎやかさや自己主張の一部として受け入れられています。
本記事では、実体験や図解を交えながら、違いに驚くだけでなく「どう対応すればよいか」まで具体的に紹介します。
音量30の衝撃
私はテレビの音量を「20」で観るタイプです。
しかし、中国人の妻がテレビを観るときは、たいてい「25~30」。
夜にその音を聞くと「うわ、でかっ!」と反射的に声が出るほどです。
我慢できずに「ちょっと音、大きすぎない?」と伝えたところ、返ってきたのは一言。
「え?普通の音量じゃない?」
日本なら深夜に音を出すのはマナー違反とされがち。
しかし、彼らは「迷惑をかけている」という意識がまったくなかったのです。
「ボリューム下げて、近所に響くから」と注意することもあります。
同じようなことは、外でも起きました。
東京の磯丸水産で中国人の妻と食事中、近くの席にいた中国人観光客が、スマホで大音量のTikTok1を再生。
しかも、その人はまったく悪びれる様子がない。
この「耳に刺さる音」に、他の日本人もギョッとしたようでした。
このように観光地の飲食店で、近くのテーブルにいた中国人観光客が、スマホ動画を大音量で再生していた経験、あなたにもありませんか?
しかも声が大きいだけではなく、テレビやスマホの「聞く音」までもが、とにかくデカい。
「なぜこんなにうるさいの?」「配慮ってしないの?」
そう思ったことがある方は、今回の内容が役に立つかもしれません。
なぜ中国人は音を大きくするのか?
なぜそれを正しいと信じているのか?
→ 「音を出すこと」にネガティブな意味がない。「良かれと思って」大きな音を使う。
なぜ大きな音を気にしないのか?
→ 幼い頃から「にぎやかな環境」が当たり前。静けさを求める習慣がない。
なぜ周囲に配慮しないのか?
→ 「自分は迷惑をかけていない」と考えるため。音の許容度が広い。
なぜ注意されても改善しないのか?
→ 注意=「個人攻撃」と受け取ることがある。特に人前で注意されるのは「面子を潰された」と感じる。
なぜ音を共有したがるのか?
→ 楽しさを分かち合う文化(例:一緒にTikTokを見て笑う)。
図解:日中「音」感覚の比較表
| 比較項目 | 日本人 | 中国人 |
|---|---|---|
| テレビの音量 | 小さめ(家族や隣人に配慮) | 大きめ(本人が聞こえること優先) |
| 公共の場での会話 | 小声で周囲に気を遣う | 通常音量または大声でも気にしない |
| 音の感じ方 | 「うるさい=迷惑」 | 「にぎやか=活気2」 |
| 音のマナー意識 | 他人の視線や評価を重視 | 自分の快適さや自由を重視 |
✅ 日本では「静けさ=マナー」
✅ 中国では「にぎやか=楽しい」「音=交流の証」
この“あたりまえ”の違いが、摩擦の元になっています。
中国人の「声と音」が大きい背景にある5つの理由
理由①中国語の発音構造(耳障りに感じやすい)
中国語は「破裂音」「摩擦音」3「声調」が多く、日本語に比べて響きが強く聞こえます。
例えば「zh」「ch」「sh」4などの音は、馴染みのない人には喧嘩腰に聞こえることも。
実際には怒っていないのに「怒鳴ってる」ように感じるのはここから来ています。
理由②「大きな声=誠実・自信」の価値観
中国では「自分の意見をハッキリ主張する人」が好まれる文化5があります。
声が小さいと「自信がない人」と見なされることすらあります。
つまり、大きな声は礼儀正しさであり、自己表現の一部なのです。
理由③「公共より自分」優先の行動原理
中国では「公共マナー」よりも「自分の快適さ」が優先される傾向があります。
その背景には「パーソナルスペース6が狭い」「集団生活が前提」「家でも常に音がある生活」など、日常の環境の違いがあります。
理由④「にぎやか=良い雰囲気」という感覚
中国では静かすぎる空間は「活気がない」とされることもあります。
飲食店やイベント会場では、にぎやかさが歓迎ムードを作る要素になります。
静けさ=礼儀とは真逆の感覚があるのです。
理由⑤人口の多さが育てた「自己主張」文化
14億人を超える中国社会では、「黙っていたら埋もれる」現実があります。
だからこそ、「大きな声=目立てる」「アピールは生存戦略」とも言えるのです。
この文化が日常化し、声や音の大きさも無意識に習慣化されています。
対処法とつきあい方のヒント
日本人の感覚で中国人に「静かにして」と伝えても、通じないことがあります。
ではどうするか?
以下のような伝え方が効果的です。
✔ 具体的に伝える
「ちょっと静かにして」ではなく
「音量を〇に下げて」「今は夜なので〇〇が困っている」と明確に。
✔ 「マナー違反」ではなく「環境の違い」と理解する
「中国ではこれが普通なんだ」と一歩引いて考えることで、ストレスの度合いがぐっと下がります。
✔ 最後は「郷に入れば郷に従え」の一言
日本にいる間は日本のルールを伝えましょう。相手も「言ってもらわないと気づかない」場合があります。
相手に伝えるときのポイント
| よくない対応 | 文化を踏まえた対応例 |
|---|---|
| 「うるさい!」と怒る | 「ここでは音を少し下げた方がいいかも」と伝える |
| 1対1で直接指摘する | 他の人もいる場面で「みんなが気にしてるかも」と共有 |
| その場で即注意する | 後で落ち着いてから「実はさっき…」と切り出す |
日本のマナーを守ってもらいたいときは、「正しさ」よりも「気配りの形」で伝える方がうまくいきます。
「郷に入っては郷に従え」でも我慢しすぎない
確かに「文化の違い」は理解すべきです。
しかし、ここは日本。あなたがモヤモヤするのは当然です。
「注意したら怒るかも」と怖がる必要はありません。
大切なのは「日本のマナーを伝える勇気」を持つこと。
日本で日本人が無理して相手に合わせる必要はないのです。
ただし、文化の違いは説明しないと伝わらない。
「なんであんなにうるさいの?」と思ったら、それは違う文化の音量設定を持っているだけ。
怒りではなく「共有」で伝えましょう。
そして、あなたの快適な空間を守ってください。
声と音の文化的ギャップ
「中国人が“音”に無頓着に見える理由」
日本:静けさ=礼儀 → 他者への配慮重視
↓
音に敏感・気にしすぎ
中国:にぎやかさ=歓迎 → 自己主張と快適さ優先
↓
音は「空気」なので気にしない
読者のあなたへ
異文化の違いを“知識”で終わらせず“行動”に変えたいあなたへ
▶X(旧Twitter)フォローはこちら :@ST__Culture(中国文化や異文化理解の情報を毎日発信しています)
▶note版でも記事配信中 → note.com/stchinach
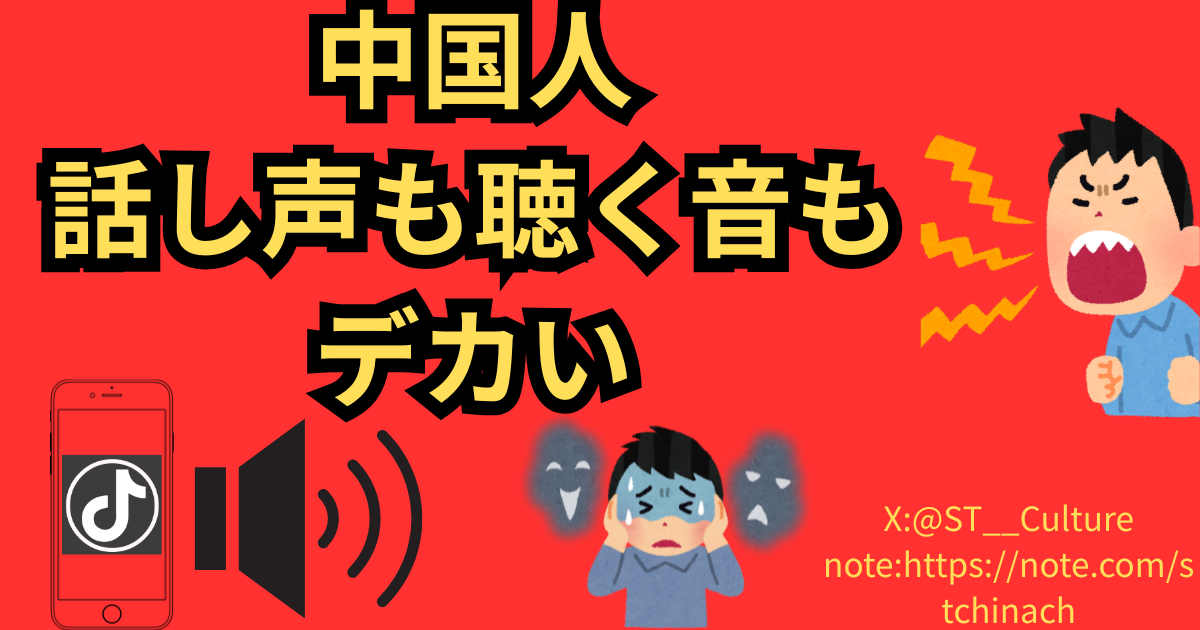


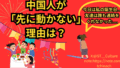
コメント