【更新日:2025年7月25日】
「あなた、本当に日本人ですか?」
「中身は中国人みたいですね」
SNSで発信をしていると、こうした言葉を投げかけられることがあります。
私は日中関係をテーマに、小紅書(RED)1やX(旧Twitter)で情報発信を続けています。
文化の違い、感覚のずれ、歴史認識の違い。
中国で暮らし、学んだ経験を元に、なるべく丁寧に、相手を攻撃しないように気をつけて書いてきたつもりです。
しかしある時、炎上しました。
炎上したのはこんな人たちでした
中国のSNSでは、本名より「ニックネーム文化2」が主流。
責任の所在が曖昧になりやすく、普段の生活では出ないような強い言葉や感情が、爆発するように出てきます。
中でも、攻撃的なユーザーにはいくつかのタイプがあると感じました:
| タイプ | 特徴 |
|---|---|
| 感情爆発型 | 「黙れ!」「中国を侮辱するな!」など突然怒りを爆発させる |
| 歴史カード3型 | 日中の話題に関係なく、過去の戦争や歴史問題を持ち出して非難する |
| ダブルスタンダード4型 | 日本人には厳しいのに、中国人には甘い |
| すり替え型5 | 話の本題と無関係な話を持ち出して論点をそらす |
| 論破した感6型 | 「論破成功w」など、勝ち負けにこだわる反論をする |
読解力7がない、バカだ、性格が悪い。
そんなことを平気で書き込むアカウントもいます。
でも、よく見ると、
- 使っている言葉のテンプレ化
- 他の投稿でも同様の言動
- プロフィールが政治的 or 空白
共通点が多く、個人ではなく「集団の圧力」に近いものを感じました。
実際にきたコメントがこちらです。






主張を曲げたらそれまで
発信をしていると、読まれずに切り取られ、攻撃されることがあります。
しかし私は、「主張を曲げたら、その主張は終わり」だと思っています。
相手の反応に怯えて表現を控えるようになったら、そもそも発信する意味がない。
だからこそ、次の3つを意識して発信設計をやり直しました。
対話を生むための発信設計8【3ステップ】
| ステップ | 具体的にやったこと |
| 1. 対象を明確に | 「この投稿は、中国文化に関心のある人向けです」と冒頭で明記 |
| 2. 目的を明示 | 「炎上させるためではなく、違いを理解するための発信です」と宣言 |
| 3. 対話を促す設計 | コメントに「あなたの経験もぜひ教えてください」と書き添える |
この3つをするだけで、
✔ 批判の数が減る ✔ 共感コメントが増える ✔ フォロワーの質が上がる
という変化が出ました。
SNSに「対話できる人」を選ぶ設計をしていなかっただけだったんです。
群衆心理と同調圧力の正体
中国のSNSにいる一部のネット民の言動には、「個人」より「群れ」の心理が色濃く出ます。
たとえば、
- 1人が「これは反日だ」と言い出すと、同調する声が一気に増える
- 誰かが「こんなの間違ってる」と書けば、それが「正解」として拡散される
これらは、群衆心理(群れで動きたい)や同調圧力9(周囲と違う意見を言いたくない)から生まれる現象です。
言い換えれば、「安全な側」にいれば安心という心理です。
飲み込まれずに自分の言葉を持つ
ネットの中には、現実よりずっと感情的で攻撃的な人がいます。
しかし、そのすべてに腹を立てていたら、きっと発信は続けられません。
大事なのは、「何を伝えたいのか」をぶらさないこと。
そして、誰に向けた言葉なのかを、最初に決めておくこと。
主張を曲げたら、その主張は弱くなる。
相手を選び、言葉を選び、自分の足で立つ。
それが、ネット社会で飲み込まれずに発信を続ける、唯一の道なのだと思います。
注釈
- 中国版InstagramのようなSNS。主に写真や生活情報を投稿する。 ↩︎
- インターネットで使うニックネーム文化。本名ではない名前。 ↩︎
- 話題に関係なく、過去の歴史問題を持ち出して反論すること。 ↩︎
- 自分と他人に違うルールを使う不公平な考え方。 ↩︎
- 本題と無関係な話に話題を変えるタイプの反論。 ↩︎
- 論理的に勝ったように見せかける発言のこと。 ↩︎
- 文章や話の意味を正しく理解する力。 ↩︎
- 投稿の内容・対象・ルールをあらかじめ決めて書くこと。 ↩︎
- 周りに合わせないといけないという空気・心理。 ↩︎
もっと深く知りたい方は、X(@ST__Culture)をフォローしてください。


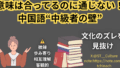
コメント