【更新日:2025年7月24日】
この記事はこんな人へ
- 中国語を勉強しているけど、最近「通じない」と感じ始めた人
- 中国人と会話や仕事をしていて「ズレ」を感じる人
- 「なぜか好かれない」「避けられている気がする」と悩む人
結論:言葉の“意味”じゃなく“概念”がズレている
中国語をある程度勉強してきた人ほど、こんな壁にぶつかります:
- 意味は合ってるはずなのに、相手の反応が冷たい(例:笑顔で「歩み寄りましょう」と言ったら相手が黙り込んだ)
- 優しさで言った言葉が、なぜか怒られる
- ちゃんと丁寧に言ったのに「通じない」
それ、あなたの語彙力の問題ではありません。
問題は「意味の翻訳」ではなく、「概念の翻訳」が抜けていること。
つまり
同じ単語でも、前提・価値観・文化的な背景が違うと「ズレ」が起きる
ということです。
10の誤解と“ズレの正体”一覧表(保存推奨)
| ❌ よくある誤解 | ✅ 実際のズレ | 🔍 背景にある文化の違い | ⚠️ 起こりうる誤解・衝突 |
|---|---|---|---|
| 辞書で通じる | 通じるのは“概念”が一致したときだけ | 単語だけ覚えても、文化がズレていたら誤解される | 意図せず相手を不快にさせる |
| 微辣1=ピリ辛 | 微辣でも激辛な場合も | 中国人の辛さ耐性の平均値が高い(感覚の基準が違う) | 「辛さわかってない」と思われる |
| 歩み寄り=やさしさ | 「譲る=負け」と見なされる | 中国では「引いた方が劣位2」と捉える勝負文化3 | 一方的要求と受け取られる |
| 客観4=中立性 | 「味方してくれる人」こそが中立 | 立場で判断する傾向がある(感情重視) | 「冷たい人」と誤解される |
| 不利=仕方ない | 「裏がある」と感じる | 条件の“平等性”よりも“損得”や“罠”を意識する現実主義 | 疑念や不信感を持たれる |
| 郷に従え=常識 | 他国には従わない、自国では従わせる | 中国では大国意識5から「自分基準6」が強い傾向 | ダブルスタンダード7だと感じられる |
| 辞書で完璧 | 文脈8・空気感がズレる | 辞書は構造、でも“血の通った言葉”は現場で学ぶ | 空気を読まない人と誤解される |
| 先生が教えてくれる | 教師も概念ズレに無自覚なことが多い | 文法・単語中心の教育が主流 | 教科書通りなのに通じない壁にぶつかる |
| 通じない=実力不足 | 語彙力はあっても伝わらない | 問題は「地図が違う」こと(認知フレーム9) | 自信喪失・発言控えがちに |
| 単語=ゴール | 単語は音階練習、伝わるのは“楽曲” | 概念翻訳10=文化を含んだ伝達力 | 会話が噛み合わず孤立することも |
なぜ“概念のズレ”が起きるのか?3つの構造
1. 認知座標軸の違い
「微辣=ピリ辛」だと思ったら、汗が止まらない。
同じ「辛い」でも、感覚の出発点が違えば、刺激の閾値も違う。日本と中国では、文化的な「味覚の基準点」がズレているのです。
2. 価値観の重力差
「歩み寄ろう」が「やさしさ」として通じない。
日本では調和=美徳ですが、中国では譲歩=弱さ。相手の文化では何が「強さ・弱さ」と定義されるのかが異なります。
3. 判断基準のフレーム差
「客観的に判断しよう」が通じない。
日本では「無色透明な判断」が良しとされるが、中国では「自分の味方こそが中立」というフレームがある。何を「公平」と見なすかの基準が違うのです。
“文化ごと訳す”という視点
どうすれば通じるのか?
- 単語を覚えただけでは不十分
- 相手の文化でどう感じられるかを想像する
- 「言葉の意味」ではなく「その言葉が生きる背景」を考える
つまり、辞書ではなく、文脈を読む力が必要なのです。
今日からできる「辞書を閉じる習慣」
- 相手がよく使う言葉を「どういう場面で」使うか観察する
- 意味がわかっても「どう受け取られるか?」を考える
- 辞書で納得する前に「その言葉が生きる空気」を感じ取る
- Before:「なぜ伝わらない?」→ After:「これなら誤解されない」
まとめ:通じるより「響く」言葉を使おう
「譲るのは大事だよね?」
「いや、それ負け宣言でしょ?」
たったひと言で、空気が凍ることがある。
中国語の本当の壁は、発音でも語彙でもなく、「概念の違い」です。
あなたがどれだけ丁寧に話しても、文化的なズレに気づけなければ、言葉は届きません。
通じる言葉を超えて、「響き合う概念」を届けるために。
辞書を閉じて、その言葉が生まれた文化に耳をすませてみましょう。
注釈
- 中国語で「少し辛い」の意味だが、日本人にとってはかなり辛いこともある。 ↩︎
- 譲った側が“弱い”と見なされる文化的価値観。日本では逆に美徳とされる。 ↩︎
- 中国では「引くと負け」「強く出ることが正しい」とされる文化的傾向のこと。 ↩︎
- ここでは「中立的・公平な立場で見ること」という意味。中国では「味方かどうか」が優先される。 ↩︎
- 自国を他国よりも優れた存在と考える意識。特に国際関係で影響を与える概念。 ↩︎
- 自分の国のルールや考え方を基準にして、他国でも同じように振る舞うこと。 ↩︎
- 同じ場面で二重の基準を使うこと。 ↩︎
- ある言葉が使われる前後の流れや空気感のこと。 ↩︎
- 人が物事を理解するときの“思考の枠組み”。文化によって異なる。 ↩︎
- 単語の意味だけでなく、背景にある価値観や文化まで理解して伝えること。 ↩︎
▶ フォローはこちら(異文化理解のヒント毎週更新中)
X(旧Twitter):@ST__Culture
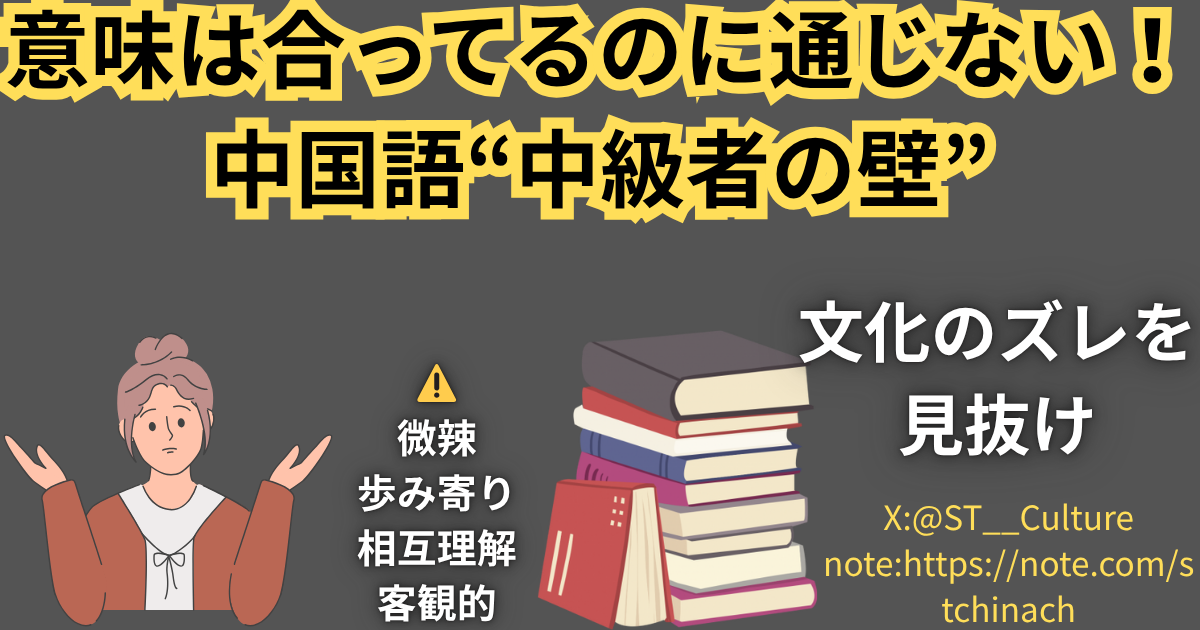

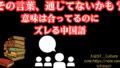
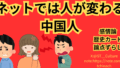
コメント