【更新日:2025年7月21日】
意味が合ってるのに伝わらない
「不公平だよ」
「えっ?それ、どういう意味?」
私はある日、中国人の知人にこの言葉を言ったとき、相手の反応に少し戸惑いました。
確かに日本語としては正しい。中国語1に訳しても意味は合っているはず。
しかし、通じない。
そんな経験、ありませんか?
本記事では、中国語において「意味は合ってるのに通じない」原因を解き明かしながら、「なぜ日本人と中国人の会話はズレやすいのか?」という根本に迫ります。
概念翻訳2のズレ
「言葉」には、「辞書的な意味3」と「概念的な意味4」があります。
たとえば「公平(gōngpíng)」は、辞書では「フェア、公平」と訳されますが、 その「公平さ」が何を基準に、どう保たれるか?という部分は文化で変わります。
つまり、
概念=言葉に対する「頭の中のイメージ5」
このイメージが、日中では大きく異なります。
しかも、それに気づかないまま会話してしまう。
この「概念のズレ」こそが、「意味は合ってるのに通じない」最大の原因なのです。
日中でズレやすい“抽象ワード”比較
| 日本語の感覚 | 中国語の感覚 | ズレの正体 |
|---|---|---|
| 公平=全員同じ条件にする | 公平=自分に不利じゃなければOK | 基準が違う |
| 中立=どちらにも味方しない | 中立=弱い側に立たないこと | 対象が違う |
| 相互理解6=50:50で歩み寄る | 理解=相手がこっちに寄ってくること | 努力の方向が違う |
| 有利・不利=客観的条件の評価 | 有利・不利=感情と損得勘定7の直感判断 | 判断軸が違う |
| 順応=場に合わせる/適応する | 順応=自分を犠牲にすること(不快) | イメージが違う |
| 平等=形の平等+機会の平等 | 平等=結果の平等に重き | 価値観の根本が違う |
どこがズレる?代表ワード7選
以下のような言葉で、日中間ですれ違いが起きがちです。
✅ 公平(gōngpíng)
中国では「公平=私にとって損じゃないか」が基準。 日本のように「ルールに従って平等に扱う」ことを求めると、冷たい印象を与えることも。
✅ 中立(zhōnglì)
日本では「両者の間に立つ」ことですが、中国では「強い者の肩を持たない」の意味も強く、 時に“中立=何もしない卑怯者”と思われることがあります。
✅ 相互理解(hùxiāng lǐjiě)
日本人は「半分ずつ譲ろう」と考えがちですが、中国では「相手がこっちの状況を理解すべき」と一方的に期待されることも。
✅ 不利(bùlì)・有利(yǒulì)
日本では客観的判断ですが、中国では「損した気がする」「得した気がする」で反応が変わります。 理屈より“感情的直感”が勝ちやすい場面です。
✅ 適応・順応(shìyìng/rùxiàng suí sú)
「順応してください」と言うと、中国人には「自分を殺せ」と聞こえることもあります。 「適応=自分を壊す」と捉えられるリスクがあるのです。
✅ 平等(píngděng)
日本では「スタートラインの平等」、中国では「ゴールの平等」に近い。 成果を平等に配分することが求められる場面も多く、会社や教育現場では注意が必要です。
なぜ「ズレ」が起きるのか?
日本と中国の“概念”がズレる4つの構造
| 観点 | 日本 | 中国 |
|---|---|---|
| 歴史的背景 | 村社会重視/和をもって貴しとなす | 儒教思想/上下・序列を重視 |
| 教育制度 | 詰め込み型8/受動的に正解を覚える | 論理型9/自分の意見を述べる訓練 |
| 感情処理 | 察して空気を読む/我慢が美徳 | 感情を言葉に出す/主張することが正当 |
| 権利意識10 | 集団の和を守る11/出る杭は打たれる | 自己主張12が当然/個の権利を重視 |
「辞書を引けばOK」が通じない時代
たとえば「中立13」という言葉を辞書で引けば、「どちらにも偏らない立場」と書かれています。
しかし、実際はどうでしょうか?
中国では「中立ってことは、味方してくれないってことだよね?」と受け取られ、関係性にヒビが入ることも。
つまり、辞書の言葉をそのまま口にするだけでは、相手の頭の中には届かない。
むしろ、誤解というリスクを背負う時代に入っているのです。
どうすれば伝わるのか?対処法3ステップ
① 言葉の背後にあるイメージを確認する
「公平って、どういう状態だと思う?」と質問するだけで、相手の思考の型が見えてきます。
② 言葉で補足せず、例え話14で伝える
「たとえば、みんなに同じだけ配るのが公平? それとも必要な人に多く渡すのが公平?」と比喩15を出すと、理解の接点が生まれます。
③ 相手の基準ごと受け止め、そこから交渉する
「その考え方もあるね。でも、私の国ではこうなんだ」
文化の違いを一度認めてから歩み寄る姿勢が信頼につながります。
まとめ|辞書を閉じて、相手の頭の中へ
大事なのは、正しい訳語ではなく、「伝わるイメージ」
あなたが言葉を使うたびに、相手はその言葉の背景まで受け取っています。
「通じた」と思った瞬間こそ、危険かもしれない。
辞書を閉じて、相手の頭の中を旅する16。
それが、異文化17との真のコミュニケーション18ではないでしょうか。
注釈
- 中国で使われている言葉。日本語とは文法や意味の感覚が違うことがある。 ↩︎
- ある言葉の意味だけでなく、その言葉が生まれた背景や考え方ごと別の言語に置きかえること。 ↩︎
- 単語の意味を調べるときに出てくる、決まった定義のこと。 ↩︎
- 単語が持っているイメージや使い方の雰囲気のこと。 ↩︎
- 言葉から頭の中に浮かぶ印象や考え方。 ↩︎
- お互いのことをわかり合おうとすること。 ↩︎
- 自分にとって得か損かを計算すること。 ↩︎
- 大量の知識を一気に覚える勉強の方法。 ↩︎
- 考えの順番やつながりを大事にして考える方法。 ↩︎
- 「自分はこうしてもいい」という気持ちや考え方のこと。 ↩︎
- みんなが仲良くうまくやっていけるようにすること。 ↩︎
- 自分の考えをはっきり言うこと。 ↩︎
- どちらの味方もしない、真ん中の立場にいること。 ↩︎
- わかりやすく伝えるために、似た話を使って説明すること。 ↩︎
- あるものを、似たイメージの別のもので言いかえること。 ↩︎
- 言葉の意味だけにとらわれず、相手の考え方や気持ちを想像すること。←この表現全体に注釈が必要です。 ↩︎
- 自分の国や生活と違う、他の国の考え方や文化のこと。 ↩︎
- 相手とやりとりをして、お互いにわかりあうこと。 ↩︎
🟡Xフォローはこちら → @ST__Culture
🟡note版はこちら → https://note.com/stchinach/n/nxxxxxx
🟡中国との違いにモヤモヤしたら、関連記事もぜひご覧ください。
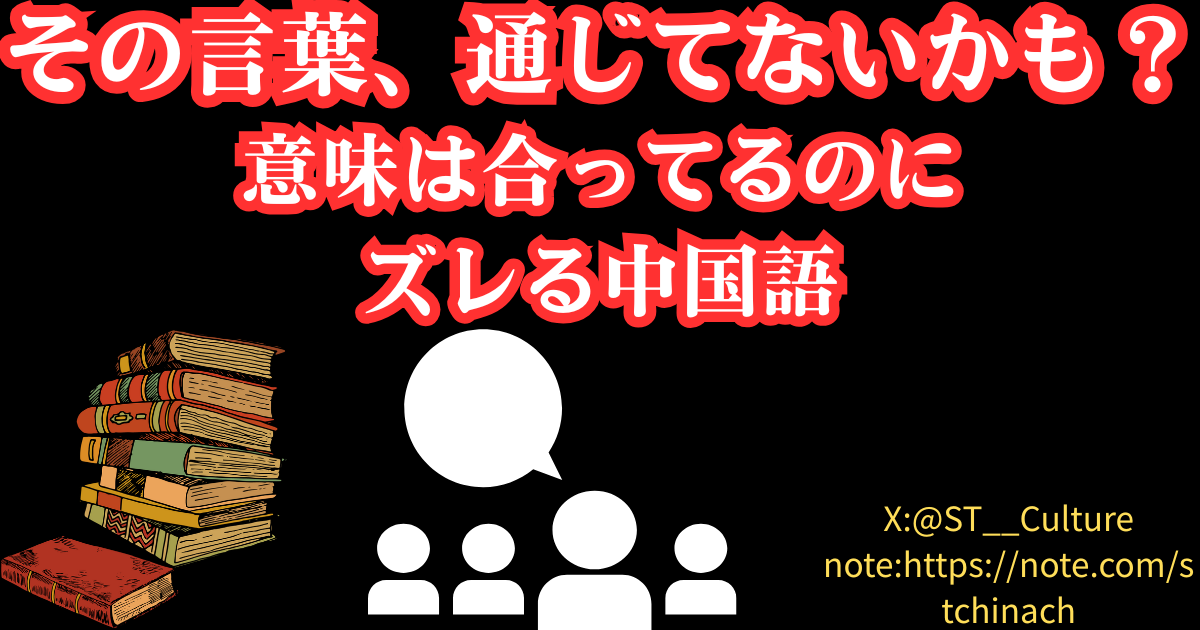

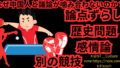
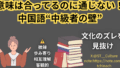
コメント